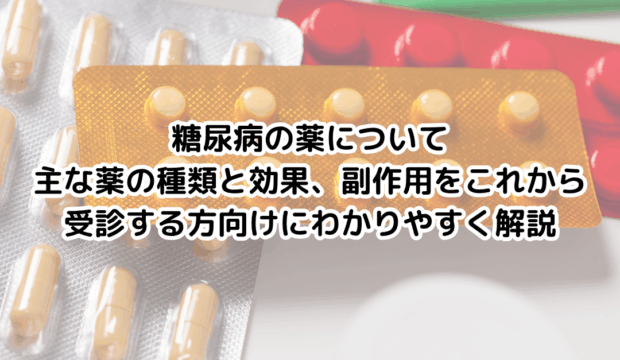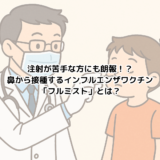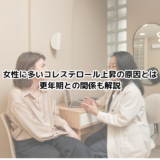目次
はじめに:糖質制限ダイエットとは?基本的な仕組みを解説

糖質オフのダイエットをやったことあるけど、結局リバウンドしてしまった

色々なダイエット試したけど結局うまくいかない

白米を食べない方がいいと言われて続けているがなかなか体重が減らない
糖質制限ダイエットの基本ルール
糖質制限ダイエットとは、炭水化物(糖質)の摂取量を制限し、血糖値の急上昇を防ぐことで体脂肪の蓄積を抑えるダイエット法です。通常の食生活では、ご飯やパン、麺類などの主食を中心に糖質を多く摂取しますが、糖質制限ではこれらの摂取を減らし、代わりにタンパク質や脂質を多めに摂ることで、エネルギー源を糖質から脂質に切り替えます。
糖質を制限すると体はどう変わる?
糖質制限を行うと、体内で以下のような変化が起こります。
- 血糖値の急上昇を防ぐ
→ インスリンの分泌が抑えられる - 脂肪がエネルギー源として使われる
→ 体脂肪の燃焼が促進される - ケトン体の生成
→ 糖質不足時に脂肪が分解されてエネルギー源になる
これらの働きによって、糖質制限ダイエットは体脂肪の減少や血糖コントロールの改善が報告されており、一定の効果が期待されます。
糖質制限ダイエットのメリット|生活習慣病予防への影響
※これらのメリットは普段から炭水化物を多く摂っている方が制限した場合のメリットとなります。その点に気を付けて読んでください
血糖値の安定化とインスリン抵抗性の改善
糖質を摂取すると、血糖値が急上昇し、それを下げるためにインスリンが分泌されます。糖質の過剰摂取が続くとインスリンの効きが悪くなる「インスリン抵抗性」が生じ、膵臓に負担がかかり、最終的には糖尿病へと進行するリスクが高まります。糖質制限により血糖値の急激な変動を抑制でき、インスリンの分泌量を適切な範囲に保つことでインスリン抵抗性を改善できます。さらに、血糖コントロールが安定すると空腹感や食後の眠気が減少し、日常生活における集中力や活動性も向上します。
体脂肪の減少と肥満予防
糖質摂取を抑えることで、身体は糖質の代わりに脂質を主なエネルギー源として利用します。この状態を「ケトン体生成状態(ケトーシス)」と呼び、脂肪燃焼が促進されます。特に、内臓脂肪は他の脂肪より燃焼されやすく、内臓脂肪が減ることで糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病のリスクを大きく低減できます。また、脂肪がエネルギーとして効率的に利用されることで基礎代謝も改善され、太りにくく痩せやすい身体づくりに役立ちます。
メタボリックシンドロームの改善
糖質を過剰に摂取すると、体内で利用されない糖質が脂肪として蓄積され、特に内臓脂肪が増加します。この内臓脂肪の増加はメタボリックシンドロームの要因となり、高血圧や脂質異常症、糖尿病を引き起こします。糖質制限を行うことで内臓脂肪の蓄積を抑制、血液中の中性脂肪や悪玉コレステロールの数値も改善されることが報告されております。結果として血圧や血糖値の安定化が進み、動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中などの心血管疾患のリスク低下につながる可能性も示唆されています。
さらに、糖質制限は食欲抑制効果もあり、過度な食事制限をせずとも無理なく減量を継続できます。適切な糖質制限を長期的に続けることで、健康的な体重管理が可能となり、健康寿命の延伸にも貢献します。
糖質制限ダイエットのデメリット|健康へのリスクとは?

エネルギー不足による体調不良
糖質は主要なエネルギー源であり、極端に制限すると、めまい・倦怠感・集中力低下などの症状が出ることがあります。特に活動量が多い人や運動習慣のある人はエネルギー不足になりやすく、仕事や運動のパフォーマンスが低下する可能性があります。そのため、自身のライフスタイルや活動レベルに応じて適度な糖質摂取を心掛けることが重要です。
食物繊維不足による便秘のリスク
糖質制限を実践すると、ご飯やパン、麺類といった主食を減らすため、食物繊維の摂取量が不足する傾向があります。これが原因で便秘を引き起こしやすくなることがあります。便秘は腸内環境を悪化させるだけでなく、免疫力の低下や肌荒れの原因にもなります。糖質制限中は、野菜、きのこ、海藻、ナッツ類など食物繊維が豊富な食品を積極的に取り入れることが推奨されます。
長期的な健康リスク
極端な糖質制限を長期間続けると、身体に必要な栄養素が不足し、栄養バランスが崩れてしまうことがあります。その結果、筋肉量の低下や基礎代謝の低下が起こり、リバウンドしやすい体質になってしまうリスクがあります。また、ホルモンバランスの乱れや骨密度の低下、腎機能の負担増加などの健康リスクも懸念されます。特に高齢者、女性、妊娠中や授乳中の方、成長期の若年層は、極端な糖質制限を避け、医師や栄養士の指導の下、適切な糖質摂取量を確保しながら健康管理を行うことが重要です。
糖質制限は誰に向いているのか?必要な人・不要な人の違い
糖質制限が必要な人
- 糖尿病やインスリン抵抗性がある人
- メタボリックシンドロームのリスクが高い人
- 内臓脂肪を減らしたい人
糖質制限が不要な人・注意が必要な人
- すでに糖質を制限している人(1日の総摂取カロリーに対して50%以下)
- 筋肉量を増やしたい人(アスリートなど)
- 低血糖になりやすい人
- 成長期の子どもや妊娠中の女性
糖質制限が適しているかどうかは、現在の糖質摂取量や体質、健康状態によって異なります。
糖質制限よりも脂質制限が推奨される理由とは?
糖質制限ダイエットは近年非常に注目されていますが、実際の栄養指導の現場では、脂質制限が推奨されることが多くあります。私も基本的には脂質制限による減量を推奨し、その主な理由は以下の通りです。
そもそも糖質が過剰ではない人が多い
現代では食生活の多様化が進み、必ずしも糖質摂取が過剰とは言えないケースが増えています。一方で、ファストフードや加工食品、外食の増加などにより、脂質を過剰摂取している人が多くなっています。特に脂質はカロリー密度が高いため、少量でもカロリーが高くなりがちです。そのため、脂質を制限することによって、より効率的なカロリーコントロールが可能になります。
初心者には脂質制限が継続しやすい
糖質制限では主食である米やパン、麺類を極端に減らす必要があり、日常の食事内容を大きく変える必要があります。また、糖質量の計算や食材選びに手間がかかるため、初心者にとっては心理的・実務的なハードルが高くなります。これに対して脂質制限は、「揚げ物を控える」「マヨネーズやドレッシングを控える」「肉の脂身を避ける」といった簡単な指針で取り組めるため、初心者でも無理なく継続することができます。
私は患者さんへ脂質制限を説明する場合、1日に摂取できる脂質の量を伝えてます。おおよそ40-60g/日です。基本的には油を極力使わないように調理をしてもらい、コンビニ購入する場合も1日摂取できる脂質の量を伝えているので、栄養成分をみたら脂質の量を簡単に把握することができます。一方炭水化物の場合、600-1200kca/日となるため計算がやや煩雑となり、面倒なため炭水化物制限による減量が長続きしない要因の一つになっています。
健康リスクを抑えながら安全に減量できる
糖質制限ダイエットを極端に行うと、エネルギー不足による疲労感や集中力の低下、便秘、筋肉量の低下といった副作用が現れる可能性があります。特に運動習慣がない人や高齢者の場合、栄養バランスが崩れることによって健康リスクが高まります。一方、脂質制限では必要な糖質やタンパク質を適切に摂取しながら、過剰な脂質をカットできるため、健康リスクを最小限に抑えながら減量効果を高めることができます。
さらに、脂質制限は生活習慣病予防にも優れています。脂質の摂取を抑えることにより、血中のLDLコレステロールや中性脂肪を減少させることができます。これにより動脈硬化や心疾患、脂肪肝といった病気の予防につながります。特に内臓脂肪型肥満の方にとっては、脂質を制限することが健康維持の上でも非常に有効です。
また、脂質制限の方が食事の満足感を維持しやすいこともメリットです。糖質はエネルギー源として重要であり、適度に摂取すれば食後の満足感や空腹感のコントロールが容易です。脂質制限をしながら適切な糖質やタンパク質を摂取することで、空腹感やストレスを軽減し、結果的に長期的なダイエット成功率を高めることができます。
以上のような理由から、多くの人にとって糖質制限よりも脂質制限の方が取り組みやすく、安全かつ健康的に減量を進められるのです。
まとめ:糖質摂取量に応じた制限が重要!脂質制限とのバランスを考える
糖質制限ダイエットは、血糖値の安定や体脂肪の減少に効果的で、生活習慣病の予防に役立ちます。ただし、糖質の摂取量がそれほど多くない人や、初心者には脂質制限の方が適している場合があります。
結論:糖質の摂取量を考慮し、必要に応じて糖質制限を行う。ただし、最初の減量では脂質制限の方が推奨されることが多い。
【当院について】
当院は患者さんの内科的治療はもちろんのこと、病気にならないようにする、処方だけに頼らない「予防医学」に注力したクリニックです。
併設したメディカルフィットネスジムと協力して、診察以外の時間も患者さん、利用者さんに付き添い、日常生活に溶け込んだ医療を提供します。
〜外来紹介〜
・生活習慣病外来
・肥満外来
・睡眠時無呼吸外来
・禁煙外来
・頭痛外来
・アレルギー外来
・各種ワクチン接種

【医師紹介】 野呂 昇平
【各種資格】
・救急科専門医
・産業衛生専攻医
・脳神経外科専門医
・脳卒中専門医
・脳血管内治療専門医
・日本医師会認定健康スポーツ医
・産業医
・健康運動指導士
・公認パーソナルトレーナー(NSCA-CSCS/CPT)
〜予約について〜
当クリニックは完全予約制です。下記ボタンより予約可能となっております。