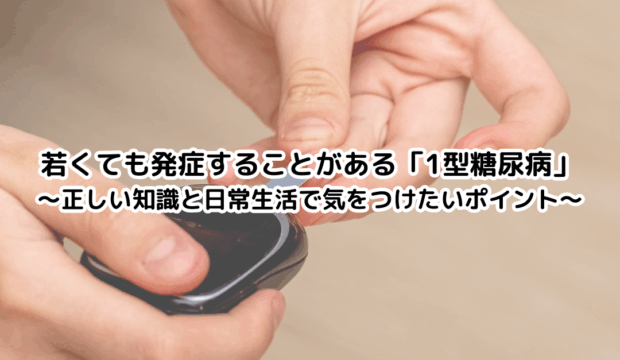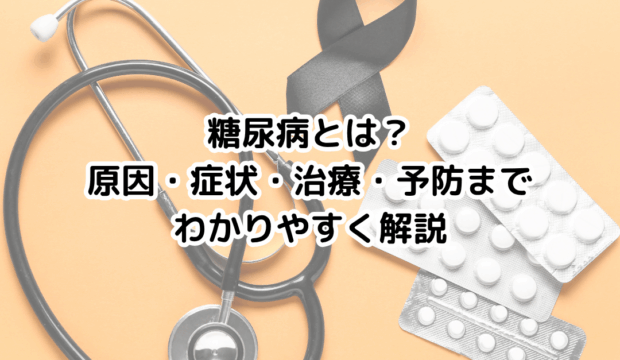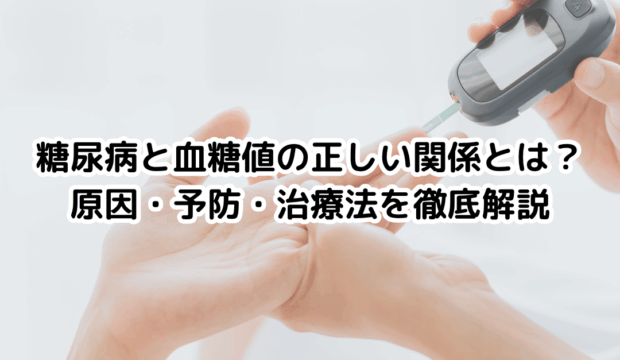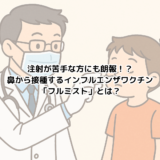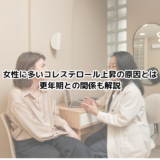目次
はじめに

アルコールが身体に良くないのは知っているけど、どれくらいまでなら大丈夫?

食事もあまり食べないようにしているのに体重が減らない

お酒飲んでも二日酔いにならないし私は大丈夫!
皆さん、お酒って美味しいですよね。飲みすぎると身体に良くないですが、適度な飲酒は健康に良いと言われております。実は、それは精神的な健康を指しており、ストレス軽減、アルコールによるコミュニケーションによるメンタルヘルスケアの要素と指摘されております。最近では身体的にはアルコールは少量でも飲まない方が長生きできるという報告もあります。本日は「飲酒と生活習慣病の関係性」について解説し、適量のアルコールについてまとめてみました。ぜひ最後までご覧ください!
飲酒と生活習慣病の関係とは?
飲酒の習慣が健康に及ぼす影響
適度な飲酒はリラックス効果や血行促進に役立つとされていますが、過剰な飲酒はさまざまな生活習慣病を引き起こす要因となります。
厚生労働省によると、日本人の約30%が何らかの形で飲酒を習慣化しており、その中には適量を超えて摂取する人も少なくありません。
生活習慣病とは?
生活習慣病とは、日々の食事や運動、喫煙、飲酒などの生活習慣が原因で発症する病気の総称です。代表的なものには、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肝疾患、がんなどがあります。
特にアルコールは、肝臓や心血管系に負担をかけ、長期的に健康リスクを高める要因となるため、注意が必要です。
アルコールが引き起こす生活習慣病の種類
肝臓への影響:脂肪肝・肝炎・肝硬変
アルコールの主な代謝は肝臓で行われますが、飲み過ぎると肝細胞がダメージを受け、脂肪肝やアルコール性肝炎、さらには肝硬変や肝がんのリスクが高まります。飲みたくないのに次の日も飲酒してしまう方はアルコール依存症の可能性が高く、専門医への相談をお勧めします。明日から我慢するから受診したくないと考えているかもしれませんが、1日も我慢できていないことは立派な病気です。自分一人で解決せず、専門家に相談しましょう!
高血圧と心血管疾患
アルコールは血圧を上昇させる作用があり、長期的に飲み続けると高血圧の原因となります。
さらに、動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まる可能性があります。
糖尿病とアルコールの関係
飲酒は血糖値を乱し、インスリンの働きを妨げることが知られています。特に過度の飲酒は2型糖尿病のリスクを高めるため、注意が必要です。
肥満やメタボリックシンドローム
アルコールにはカロリーが含まれており、過剰摂取するとエネルギー過多になり、内臓脂肪が増えやすくなります。肝臓は身体の中でも脳や筋肉に次いでカロリーを消化してくれます。内臓脂肪が増え、脂肪肝が進行することで痩せにくい身体ができるため、食事を抑えた減量を行っても中々体重が減りません。皆さんも経験はないでしょうか?
がんのリスク
世界保健機関(WHO)によると、アルコール摂取は口腔がん、咽頭がん、食道がん、肝がん、乳がんなどのリスクを高めることが報告されています。
特に飲酒と喫煙を組み合わせると、そのリスクはさらに上昇します。
適量のアルコールとは?健康を維持する飲酒量
適量の目安
厚生労働省が示す「健康日本21」では、1日当たりの純アルコール摂取量は男性で20g、女性で10g程度が適量とされています。
具体的な飲酒量の目安としては、以下の通りです。
- ビール(5%)
… 500ml(中瓶1本) - 日本酒(15%)
… 180ml(1合) - 焼酎(25%)
… 100ml - ワイン(12%)
… 200ml - ウイスキー(40%)
… 60ml(ダブル1杯)
適量を超えた場合のリスク
1日あたりのアルコール摂取量が男性40g、女性20gを超えると健康リスクが急上昇します。
特に長期間にわたる大量飲酒は、前述した生活習慣病の発症リスクを大きく高めます。女性は男性に比べ、アルコール摂取量が半分以下に設定されており、男性と同じような飲み方をするとアルコール性肝硬変や膵炎を発症しやすいです。
※私の経験上、救急車で運ばれてくる急性膵炎の女性はアルコール性が多い印象です。主婦の方は日中から飲酒をしていることが多く、いわゆるストロングゼロ(アルコール含有量9-10%)を1日1L以上飲みます。500ml缶2本で1L飲んだ場合、純アルコールで約100gも飲酒していることになるため非常に危険です。
アルコールの分解能力には個人差がある
日本人の約40%は、アルコール分解酵素(ALDH2)の活性が弱く、少量の飲酒でも悪影響を受けやすい体質です。
このため、「適量」には個人差があり、自分の体質に合った飲酒量を知ることが重要です。
飲酒習慣を見直すポイントと健康的な付き合い方
休肝日を設ける
毎日飲酒するのではなく、週に2〜3日は休肝日を作ることで肝臓の負担を軽減できます。私が普段診察していると、なかなか休肝日を作れない人がいます。その場合は「アルコールを我慢できないなら休肝日を作れない分、運動してください!」と伝えます。アルコールも我慢できない、運動もできない人は性格的に我慢ができないタイプも多く、生活習慣の改善が難しい場合、生活習慣病が起こりやすい傾向があります。。
水を飲みながらお酒を楽しむ
アルコールと一緒に水を摂取することで、脱水症状を防ぎ、体への負担を軽減できます。コツとしては飲んでいるお酒と同程度の水を飲むと効果的です。
食事と一緒に飲む
空腹時に飲酒すると血中アルコール濃度が急上昇するため、食事と一緒に楽しむことが理想的です。空腹時に飲むと胃へのストレスが強くなり、また少量の飲酒でも酔ってしまうため少しでもいいので胃の中に食べ物や水を入れるようにして体調を整えてください。
ノンアルコール飲料を活用する
近年はノンアルコールビールや低アルコール飲料の種類も豊富になっており、適度に取り入れることで飲酒量をコントロールできます。
依存に注意する
飲酒が習慣化し、「飲まないと落ち着かない」と感じるようになったら、アルコール依存症の兆候かもしれません。必要であれば医師に相談することをおすすめします。
まとめ:飲酒と健康のバランスを考えよう
適度な飲酒は、リラックス効果や人間関係を円滑にするメリットがありますが、過剰な飲酒は生活習慣病のリスクを高める要因になります。
特に肝臓への負担、高血圧、糖尿病、がんのリスクを考慮すると、適量を守ることが非常に重要です。
また、アルコールの影響は個人差が大きいため、自分の体質に合った飲み方を心がけましょう。
健康を維持しながらお酒を楽しむためには、適量を意識し、休肝日を設け、生活習慣全体を見直すことが大切です。
自分に合った飲み方を見つけ、健康的なライフスタイルを送りましょう!
【当院について】
当院は患者さんの内科的治療はもちろんのこと、病気にならないようにする、処方だけに頼らない「予防医学」に注力したクリニックです。
併設したメディカルフィットネスジムと協力して、診察以外の時間も患者さん、利用者さんに付き添い、日常生活に溶け込んだ医療を提供します。
〜外来紹介〜
・生活習慣病外来
・肥満外来
・睡眠時無呼吸外来
・禁煙外来
・頭痛外来
・アレルギー外来
・各種ワクチン接種

【医師紹介】 野呂 昇平
【各種資格】
・救急科専門医
・産業衛生専攻医
・脳神経外科専門医
・脳卒中専門医
・脳血管内治療専門医
・日本医師会認定健康スポーツ医
・産業医
・健康運動指導士
・公認パーソナルトレーナー(NSCA-CSCS/CPT)
〜予約について〜
当クリニックは完全予約制です。下記ボタンより予約可能となっております。